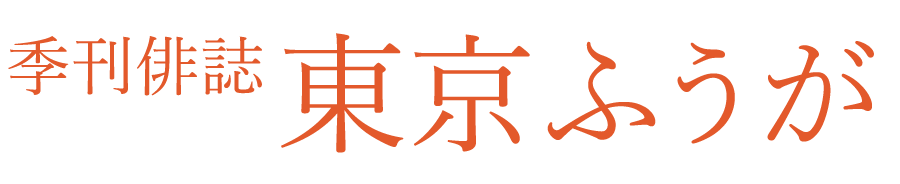曾良を尋ねて(48)
乾佐知子
140 榛名山に消えた仙人は誰か
信州の山麓にある諏訪で育ち、毎朝大社の朝太鼓で目覚め境内を遊び場としていた曾良少年は、十三歳で長島に旅立つまで、子供心にも神の崇高さや偉大さを、身に感じて成長していったものと思われる。長じて江戸に出るや公儀御用達で神道の大家である吉川惟足の門下生となり、神道家としての本格的な道を歩み出すのである。
その一方で伊勢長島では青年時代の十数年を真言宗の大智院で過ごし、仏に身近に接することにより、その教えに深い慈悲と寛容の心を学ぶこととなった。長く神仏に仕えてきた精神は、その後の彼の人間形成の上で大きな影響を及ぼしたといえよう。
曾良が榛名に籠る際に、何も持たない、無所有、無一物を志した思想は、早くは平安中期の空也から始まり、西行、一遍と続きやがてその流れは芭蕉へと繫がっていると捉えれば、曾良が多くの先人達から影響を受けていたとしても不思議ではない。
では、曾良が二度目の終焉の地に何故榛名を選んだか、という点について触れてみたい。その所以は彼の学んだ風水の方位学によるものと考えられている。
榛名山は諏訪からは艮(ウシトラ・北東八十㌔)で鬼門に当たり、日光東照宮からは坤(ヒツジサル・南西八十㌔)の裏鬼門に当たる。地図上でこの二点を線で結ぶと丁度その真中が榛名の地点と一致するのだ。まさに完璧な場所といえよう。残された身命を徳川家の為に捧げたい、その一心で幕府の許可を得た曾良は晴れて榛名の住人になったのだ。
ここで榛名山中に現れた白髪の老人の話に戻るが、彼は仙人のごとく洞窟に住んでいる、と言ったが偶然関祖衡と並河誠所に会ったときは、鍬を持っていたという。更に袂に天狗餅なる貴重な食糧を所持していたこと等から察するに、恐らく河西浄西禅師のような木喰仙人とは違い、自給自足の生活をしていたのではあるまいか。天狗餅は神社の御師が節分の際に撒くもので、数も少なく一般の人達にはなか々手に入らない貴重なものだという。御師の人々と交流がある、ということは、即ち今も幕閣と何らかの形で繫がっていると思われる。
与えられた余生をいかに処すべきか、ひたすら神仏を拝み、神道を極めんと修験者として厳しい試練を己に与える。このような曾良の生き方は一見苦しいだけの人生のように思えるが、果してそうであろうか。
封建社会の厳しい規律に縛られている世間のしがらみから解放され、人間らしい自由を取り戻した曾良にとって、この榛名での生活こそ自らが望んでいた最高の幸せの余生ではなかったろうか。並はずれた体力の持主であるからまだまだ十年位は長生きしたかも知れない。そう考えると何かほっとするのである。